さっしいの鉄道風景 <昭和50年(1975)7月- 52年(1977)7月>
⇒ ぽこぺん
昭和 42/8
43/7-8
44/2
44/3-4
44/5a
44/5b
44/6a
44/6b
44/7a
44/7b
44/8a
44/8b
44/8c
44/9
44/10
44/11-12
45/1-3
45/3-4
45/4-5
45/6
45/7
45/8
45/9-11
46/1
46/3a
46/3b
46/4-5
46/5
46/7
46/8a
46/8b
46/8c
46/8d
46/8e
46/9-10
46/11-12
46/12
47/1
47/3a
47/3b
47/3c
47/4-7
47/7a
47/7b
47/8a
47/8b
47/8-11
47/12
48/1-3
48/5-10
49/7-50/3
50/7-52/7
53/2-54/12
55/3-7
55/8
55/10-12
56/1-7
56/7-8
44/9 44/10 44/11-12 45/1-3 45/3-4 45/4-5 45/6 45/7 45/8 45/9-11 46/1 46/3a 46/3b
46/4-5 46/5 46/7 46/8a 46/8b 46/8c 46/8d 46/8e 46/9-10 46/11-12 46/12 47/1 47/3a
47/3b 47/3c 47/4-7 47/7a 47/7b 47/8a 47/8b 47/8-11 47/12 48/1-3 48/5-10 49/7-50/3
50/7-52/7 53/2-54/12 55/3-7 55/8 55/10-12 56/1-7 56/7-8
≪ 画像をクリックすると拡大表示されます ≫

大学1年の夏休み、音楽サークル「ハーモニカ・ソサエティー」の四国演奏旅行で、初めて本州を離れました。国鉄の宇高連絡線で高松へ。船上では「早稲田マーチ」を即興演奏。四国では高松・川之江・丸亀などの演奏会が優先で、鉄道を撮ったのは僅か2枚でした。これは全てのコンサートを終えた遊びの日、みんなで金毘羅さんへ参詣した帰りに高松の栗林公園まで琴電に乗る際のスナップです。ホームにいるのは皆、サークル仲間。大学生活4年間で一番の友人となるM君の姿も見えます。初めて乗る琴電は、元名鉄の車輛でした。16両の1020形は名鉄3700系を譲受したもので、1032は琴電唯一の高運転台車。名鉄時代はク2713で、事故復旧の際にこの表情に変わっていました。

栗林公園から高松駅まで歩く途中の踏切で撮った…キハ45でしょうか。首都圏色になる前のオリジナル塗装ですね。栗林駅付近では高架化工事が進められていますが、翌年に高架線となったそうです。さて、自分はサークルに入部後すぐに好きな人ができて、6月に鎌倉デート。しかし既にフラれています。この日は坂出の先輩の実家(居酒屋)で打上げコンパ。楽しく飲んでM君は酔い潰れ、多度津の宿舎裏で、夜の瀬戸内海を眺めながら失恋話を聞いてくれたのは、もう一人の友人S君でした。そのお蔭で自分の「わだかまり」も吹っ切れたのか、翌日の徳島駅前では、赤帽の僕も緑帽のS君も元気です。徳島港から夜行のオーシャンフェリーに揺られ、30日の昼に東京へ帰り着きました。

いきなり北海道、函館駅前電停です。この夏は立て続けに、本州を離れる旅を体験しました。義兄と二人で上野から座席急行「八甲田51号」で12時間、青函連絡船で4時間。朝6時に函館に着き、タクシー利用で五稜郭を見学後、駅前まで戻って、列車の発車時刻まで一人で市電を見に来ました。駅を背に、十字街方面へ向かう通りを望んでいます。停留場を出た719号は、700形ではなく710形で、スタイルはむしろ800形に酷似しています。「湯の川-5-十字街」という表示なので5系統。これから分岐を右折するところでしょう。尚、この北海道旅行の写真はネガが手元に無く、きちんと記録もしていないので、時系列が不明です。翌日以降は、日付さえも怪しくなります。

横断歩道を渡って、函館駅前交差点の東南の角に来ました。西南の角に聳える正面の建物は、今も変わっていません。「函館北洋ビル」だそうですが、当時もそうだったのでしょうか。「駒場-2-谷地」という方向幕表示の市電530号が目の前を駆け抜け、十字街方向へ走り去って行きます。500形は一見すると古い電車のように思えますが、製造初年は戦後の昭和23年。当初は3扉でしたが、後に中扉を締め切って前後の2扉を使用するようになり、更にワンマン化の際に、前部と中央部にドアのある2扉車に改造されました。後部にもドアのあった痕跡が、写真からも分かりますね。函館市電では最大の両数を誇った形式で、ラストナンバーの530号は現在も生き残っているそうです。

交差点の北西の角を望みます。写真の左手奥に国鉄の函館駅があります。市電は1000形がやって来ましたが、これはもう見てすぐ分かるように、その前身は東京の都電7000形です。正面の顔付きは少し変わって、非対称の変則2枚窓となったものの、側面は昔のままで、都電時代の面影を充分に漂わせていますね。都電7000形が大好きな自分としては、こうして異郷の地で活躍する姿に接することができて感激です。電車の方向幕には「駒場-3-ドック前」という表示。前面下には「ガス会社まわり」という注記があります。駒場車庫前発の3系統ですが、函館駅前を直進して画面奥へ続くこの線路と共に、今は廃止されています。1000形も引退し、唯一残った保存車も解体されてしまいました。

この北海道旅行は、今年3月に姉と結婚した相手、つまり和歌山の義兄と二人で計画したもので、獣医を務める弟さんの住む広尾線沿線の牧場を訪ねることが目的でした。函館駅前停留場に次々とやって来る電車は3台とも800形。昭和37年から40年にかけて新潟鐵工所にて12両作られた電車で、710形に良く似ていますが、間接非自動制御が採用されています。先頭の805号は前回の1000形と同じ「駒場-3-ドック前」および「ガス会社まわり」という表示ですが、走る方向は逆ですね。ドック前発・駒場車庫前行きの3系統ということになるのでしょう。800形は後に車体更新されて8000形・8100形となり、今は812号だけが残っています。

旅行に同行している義兄は、この時、函館の朝市へ行くと言って別行動中です。函館本線の列車の発車時刻までに駅へ戻ることになっています。写真は前回の続きで構図も似ていますが、805号の後方の804号が近付いて来ました。方向幕表示は「湯の川-5-十字街」で、窓下表示は「松風・函駅まわり」のようです。すれ違って行った電車は1004号。都電7000形を昭和45年に譲受し、前面窓は固定化・左右非対称となり、集電装置はZパンタに変わりましたが、それ以外の全体の雰囲気は昔のままでした。当初は都電の塗装のまま走っていたそうですが、翌年ワンマン化された際、前面窓の改造と共に函館市電の標準色に塗替えられました。2系統・谷地頭(やちがしら)行き。

函館駅前の交差点で、5系統同士のすれ違い。こちらへ向かって来るのは804号(800形)、向こうへ走って行くのは723号(710形)ですが、同じ顔付きですね。写真の右が国鉄の函館駅。電車は松風町方面へのカーブ線路を走っていますが、直進して画面右へ行く(ガス会社経由の)線路は後に廃止されました。この後、函館発9時40分の釧路行き気動車急行「すずらん1号」に乗り、義兄が朝市で買った鯨のベーコンを肴に、カップ酒を飲みながら、9時間半かけて帯広まで移動します。函館本線・室蘭本線・千歳線経由で、途中の札幌までは会津若松の女性二人と同席ということもあり、車中も楽しく過ごせました。札幌以降の車窓風景は、次回から少しだけお目に掛けましょう。

急行「すずらん1号」は9時40分に函館を発車。函館から長万部までは函館本線、東室蘭・苫小牧を経て沼ノ端までが室蘭本線、そして札幌の手前の白石までは千歳線を走り、そこまでで既に4時間半。かなり長い道のりでしたが、札幌で方向転換し、東へ向かって再び発車したのが14時25分。そこからも、また長い旅が続きます。札幌から帯広までの車窓は写真の順序もバラバラで、当初は場所も全く分かりませんでしたが、写った内容から考えてみると、この1枚は当時の電化区間、札幌~滝川のどこかでしょう。D51形蒸気機関車の姿も見えますが、白石・江別・岩見沢・砂川…。お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非ご教示ください。

この写真も、場所は全く覚えていませんでしたが、良く見ると、ホームに建つ電柱の左右に「平岸方面」「赤平方面」という文字の書かれた案内表示板が見えます。そうなると、赤平と平岸の間の「茂尻」駅だということは明らかでしょう。「すずらん1号」の滝川発は15時43分、赤平は56分。茂尻・平岸は通過で、次の停車駅の芦別は16時16分ですから、ダイヤ通りなら16時前後の光景ということになりそうですね。函館を出て長万部・東室蘭・苫小牧・札幌・滝川と走って来た「すずらん1号」ですが、函館本線から分岐して根室本線に入った途端、名前は「本線」でも、山へ分け入って行くローカル線という雰囲気に変わったように思います。

キハ82系のディーゼル特急「おおぞら」とすれ違いました。16時過ぎだろうという時間帯から見ると、帯広発16時19分・滝川着18時58分の「おおぞら3号」でしょう。こちら「すずらん1号」は、富良野発16時50分・新得発18時18分ですから、その間で交換設備があって、山が迫り来るような場所となると…「金山」駅あたりでしょうか。富良野・新得間は現在は廃線となってしまった区間ですが…。そして、この後、帯広に着いたのは19時9分。駅から街へ出て「帯広ラーメン」を味わい、20時48分発の広尾線に乗って、目的地の「豊似」に着いたのは22時20分。義兄の弟(近隣の牧場の獣医)に会うのは、3月に姉の結婚式で『知床旅情』を一緒に歌って以来です。

豊似では駅近くの丸福旅館に5泊滞在することになります。着いた翌日は早速、義兄の運転で襟裳岬へ。国道336号は「黄金道路」と呼ばれていますが、ゴージャスな名前とは裏腹に、凸凹ガタガタ、砂埃舞い上がる物凄い道でした。なんでも、作るのに金が掛かったので、その名が着いたとか。そして、漸くのことで辿り着いた「襟裳の夏」は、何も~無い~夏です~♪ 帰路は(かなりの距離ですが)浦河まで回り、引退した競走馬のシンザンやタケホープを見てきました。そんな豊似滞在中、この1枚は、広尾駅まで往復して広尾線の全線完乗を果たした日(8月14日)の写真ではないかと思いますが、記録が無いので、はっきりしません。鉄道への拘りが殆ど無くなっていた時期でした。

豊似に滞在中の一日、特に目的も定めず、一人でどこかへ行ってみようと、朝の一番列車(豊似6時3分発)で帯広へ出ました(7時46分着)。「北海道周遊券」は道内の国鉄路線は乗り放題。そして急行列車の自由席を無料で利用できるので、とりあえず8時38分発の気動車急行「池北(ちほく)」で北見まで行ってみようと考えました。池田までは根室本線を走りますが、幕別と思われる駅で、通過する上りの特急「おおぞら」と単線交換しました。6時45分に釧路を出た「おおぞら1号」でしょうが、帯広着は8時36分の予定。こちら「池北」が帯広を出る時刻よりも早いはずですが、かなり遅れていたのでしょうか。こちらの幕別発の予定時刻は8時52分です。

この写真の場所は全く分かりませんが、客貨混合列車に乗っていますね。6~7両のワムの後ろに、自分の乗る客車が連結されているように見えます。駅は2面3線のホームを持つ一般的な国鉄タイプ。自分の行動から考えてみると、8月15日の帰路の根室本線、池田・帯広間のどこかという可能性が高そうですが、何とも言えませんね。さて、前回の急行「池北」の話を続けると、車内では阿寒湖へ行くという東京医科歯科大学の二人の年上女性と知り合い、厚かましくも同行させてもらうことにして、足寄からバスに乗りました。阿寒湖観光の後、自分は瓶入りのマリモを買って豊似へ帰ります。帰京後、二人とは手紙をやり取りし、お互いの音楽サークルのコンサートに招待し合ったりしました。

この写真も日付や場所が全く分かりませんが、可能性としては、8月12・15・17日の根室本線か、広尾線や池北線が考えられます。ともあれ、自分が撮った鉄道の「白黒」写真は、この北海道旅行が最後となりました。16日の夜は豊似の盆踊り大会でずっと踊り続け、賞品をもらったりして、17日の朝8時20分に豊似を離れます。帯広は雨。13時29分発の「ニセコ2号」は混み合って、札幌まで立ち通しでした。札幌からは座れて快適に、往路と違う、小樽・倶知安など、函館本線経由で函館に戻ります。連絡船で青森へ渡り、18日の朝5時9分発の急行「十和田51号」12系座席客車で、ほぼ眠りながら常磐線経由、17時19分上野着。最初で最後の北海道旅行、人生でも最大となる長旅を終えました。

夏休みも終盤の9月上旬、早稲田大学の音楽サークル「ハーモニカ・ソサエティー」の夏合宿がありました。この年は北志賀高原。もちろん初めての体験です。9月5日の朝、1年生は大学の部室から楽器を運び出してトラックに積み、運転する先輩を見送り、みんなとは上野で合流して10時47分の「信州2号」で長野、1年ぶりの長野電鉄で信州中野、そしてマイクロバスで宿舎へ。合宿中は、アレンジ大会などで1年生の団結が深まり、M君やS君などの友人とも一層親しくなれて、有意義な1週間でした。帰りは湯田中にて、上野へ直通の169系急行「志賀1号」(13時20分発)を待つ間に、長野電鉄の0系OSカーを見ることができました。自分にとっては、これが19歳最後の鉄道写真となります。

20歳になって3週間。相変わらず音楽サークル「ハモソ」に浸り切った日々です。9月の夏合宿の後、10月は関西学院とのジョイントコンサートで関西へ。阪急や阪神に乗ったのに写真も撮らず、鉄道趣味からはすっかり遠ざかった感があります。11月末には初めての定期演奏会で感動。でも、時々は仲間の女の子と二人でお散歩しても恋には至らず、この2日前も1年間の「お別れコンパ」で酔ったものの、冬は3月まで活動休止で練習もありません。張り詰めたものが一気に萎んだ感じがして、そんな時、また都電への愛情を思い出したようです。ひさしぶりに見た都電は「荒川線」に変わっていて、高戸橋あたりでは線路の移設工事が進んでいました。何やら、新しい時代が始まりそうな…。

前々回の長野電鉄以降、写真の画質が良くないことにお気付きでしょう。実は、白黒写真を終了して、カラーフィルムだけを使うようになったものの、この当時はたくさん撮れるようにと、ハーフサイズのカメラをカラーに使っていました。人物のスナップには何とかなっていたのですが、やはり画像が粗く、鉄道写真には向かないようですね。それもこの年内で終わります。もう暫くご辛抱下さい。さて、昨年(昭和49年)10月から27・32系統を統合し、早稲田~三ノ輪橋の全線を「荒川線」と改称した都電ですが、電車は変わらず早稲田行きの7000形が千登世小橋を潜り抜けて来ました。向こうの車内からこちらを撮ったのは、初めて都電を撮影した日でした。もう7年半も前のことになるのですね。

千登世小橋の上から、南の「学習院下」電停方向を見下ろしています。この下の都電の線路は一日中日蔭か逆光になるためか、これまでは撮ったことが無かったアングルです。この時はまだ午前中だったのか、やはり、もろに日蔭となってしまいましたが…。並行する道路は明治通りです。自分が立っている目白通りの下を潜るために、交差地点に千登世橋を架け、新道(環状5号線=明治通り)が開通したのは昭和7年のことで、道路の立体交差としては日本初と言われているそうです。王子電気軌道のこの区間が開通したのは昭和3年の末のこと。それ以前の、北の大塚側から延びて来た路線が「鬼子母神前」止まりだった頃は、終端部に仮の車庫が設けられていたという説もあります。

鬼子母神前の電停から雑司ヶ谷方面を望むと、都電の線路は相変わらずのジェットコースターです。弦巻川の谷へ一旦下りてまた上るため、線路の縦断面は大きく凹んだ形になっています。谷底から駆け上がってきた早稲田行きの電車は、系統板に「荒川線」と表示した7059号ですが、明るい冬の日差しが当たっています。車輛は何も変わっていないのですが、「32系統」でなくなってから、早くも1年以上。新しい時代へ移りつつあることは確かでしょうね。思えば、これとほぼ同じアングルで32系統の写真を撮ったのは、6年前のことでした。それを見ると、以前は、このあたりまで、早稲田行きのホームが延びていたようですね。この後は、大塚・王子方面へ行く都電に乗ってみます。

大塚駅前で都電を降りて、少し歩いて「南大塚公園」に来ました。かつての都電大塚線(16系統)大塚車庫の裏手にあたります。ここに都電6162号が保存されていることは、当時どこから知ったのだったか…。昭和48年の高校3年の頃から、自分の鉄道趣味は一旦下火になった感があり、鉄道写真も殆ど撮らなくなっていましたが、音楽サークル活動が中休み状態になったこの時期は、なぜか急に、都電の廃車や保存車に興味を持ち始めたようです。生き生きとした現役の鉄道の活躍ぶりより、諸行無常感の漂う廃線跡や廃車体に対する愛情の方が大きくなってきたのでしょうか。この後の日々の自分の行動からも、そんな様子が垣間見られるようになります。

大塚駅前停留場まで戻って、荒川線の7515号を1枚。相変わらず、画質・発色ともに満足の行かない写真ですが、ご容赦ください。先ほどまでは7000形ばかり目にしましたが、より新しい7500形も健在です。「都電荒川線」として、将来まで生き残ってくれることでしょう。前回も触れたように、この時期は保存車に興味を持っていたようです。まだ本格的な研究は始めていないので、資料は殆ど手元に無かった頃で、『東京都交通局60年史』も見ていませんから、『都電 60年の生涯』などの書籍や『鉄道ピクトリアル』誌などの記事に頼るしか無かったと思います。この日も、帰りがけに、もう少し都電の保存車を訪ねてみますが、6080号はまだ現役だった時代で、飛鳥山公園にはいません。

一気に郊外へ…と言っても自分の住む調布市内ですが、京王線の西調布駅に近い「上石原児童公園」を訪ねてみました。中央自動車道の高架の真下の公園に都電8005号が置かれていますが、窓ガラスは全て失われ、かなり荒れた状態でした。昭和31年12月製造で広尾車庫に配置され、そこだけで一生を終わった珍しい車輛です。昭和44年2月に廃車となり、その後は、ここで過ごしたようです。この日は、京王線で仙川へ戻り、世田谷区の緑ヶ丘幼稚園の1015号も見に行きましたが、そちらは幼稚園の教室として利用され、好感が持てました。しかし立地が悪く、写真を撮ることができなかったのは残念です。本などでも、あまり見たことは無いように思います。

3月に和歌山に嫁ぎ、今は出産のため実家に帰っている姉と一緒に自宅近くを散歩しましたが、お腹の大きな女性と並んで歩くのは妙に恥ずかしくて、姉のお腹を指す矢印に「僕のせいではありません」と書いたプラカードでも持って歩きたい気分です。15分ほど歩いて三鷹市の新川南台団地を訪ねると、敷地内に都電6175号が置かれていました。団地の集会所として使われているようです。昭和26年1月に生まれ、南千住→錦糸堀→青山→大久保→青山→荒川→神明町→荒川と、あちこち転属してきました。昭和47年11月に廃車。4日前に見た8005号と同じく、この後、早い内に解体されてしまったようです。横に立つ昭和30年製の「さっしい青年」は、20歳になって、まだ1か月も経ちません。

大学1年も終わりに近い早春。授業も音楽サークルの練習も無いので、サークル仲間で国文科の同級でもあるS君と二人、和歌山の姉を訪ねる旅行を企てました。どうせなら紀伊半島を一周、それも名古屋から夜行列車でアプローチという、いささかハードな内容です。東京から各駅停車で沼津と浜松で乗換え、名古屋には夕方6時着。市内で時間を潰し、23時58分発の急行「紀州5号」のガラガラの車内で仮眠しながら那智駅へ。6時の始発バスで那智の滝を見学。駅へ戻って、ホームに面した那智海岸で1時間ほど過ごします。8時に新宮を発車した天王寺行き特急「くろしお1号」が通過しました。最後尾はキハ82。後ろから2両目と3両目はグリーン車で、次の紀伊勝浦は8時18分。

那智海岸でS君と無邪気にはしゃいだ後、未明に通った線路を再び、三重県との県境の手前の新宮まで戻りました。ある目的があって、駅から比較的近い「丹鶴城跡」を訪ねます。展望台になっている石垣の上から市内を見下ろすと、向こうには熊野灘の海が望め、手前には新宮駅構内や側線が俯瞰できました。反対側は熊野川がとても綺麗です。その川が県境で、対岸は三重県の鵜殿。今日はこの後、和歌山県の東の端から西の端まで、1本の列車で紀伊半島をぐるっと回ろうと思います。今夜は和歌山市の外れの、阪和線の紀伊駅に近い姉の家に泊めてもらう予定ですが、その前にちょっと…。この城跡の展望台へは、どうやって登って来たのでしょう。

丹鶴(たんかく)城跡(新宮城跡)へは、このケーブルカーで登りました。帰りは山上の「二の丸」駅でボタンを押すと、山麓の「丹鶴」駅から小さな搬器が上って来ます。下の駅も線路も全部見えていて、斜行エレベーターのようなものですが、これでも地方鉄道法に基づいた存在で、れっきとした私鉄(鋼索鉄道)です。乗務員は高校生ぐらいの可愛い女の子で、僕たち二人が乗込むと下の駅へブザーで知らせ、「発車しま~す♪」と言って操作しますが、その声がまた可愛らしくて…この旅行中、何度も話題になります。全長0.1km、軌間は762mm。昭和29年に「新宮観光」という会社が敷設。この当時は「近鉄観光」による経営で、後に「和歌山観光」へ譲渡され、平成元年に休止となりました。
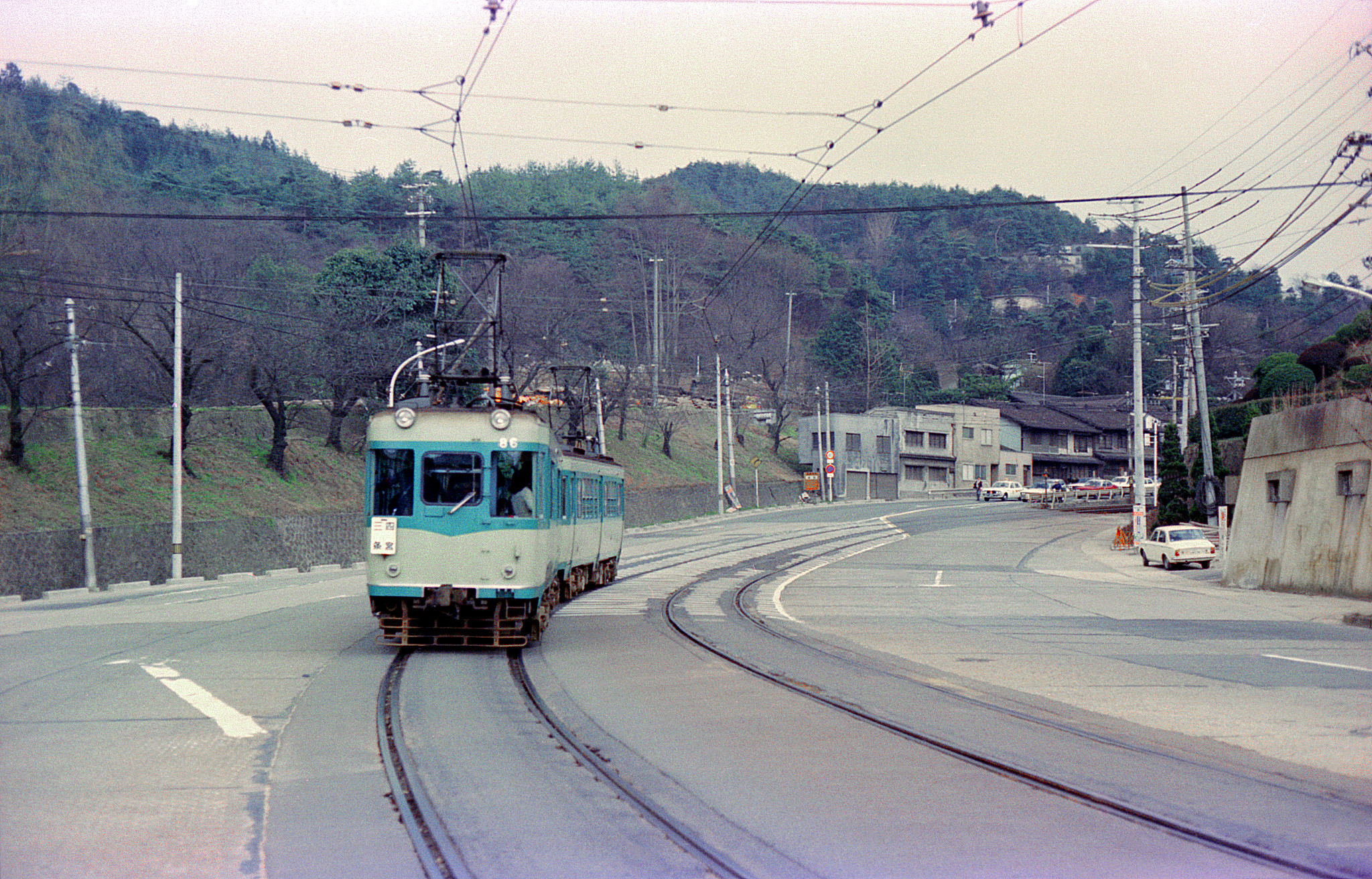
3月2日の夜はS君と二人、和歌山の姉の家に泊めてもらいました。昨年末に姉が大きなお腹を抱えて調布の我が家で出産し、既に2か月が過ぎた姪っ子とも再会。3月3日はちょうど雛祭りなので、南海電車に乗って加太の「雛流し」のお祭りを見に行きました。ところで、S君はこの1年間、はるか宇都宮の自宅から早大へ通学していましたが、さすがに大変なので、今は下宿探し中です。その都合で不動産屋に呼び出され、彼だけは予定を早めて4日に帰ることになりました。それを見送りがてら、京阪3000系でカラーテレビを見ながら京都三条へ。そして京津線で蹴上へ。6年半前に初めて見た時はポール集電だった80形も、今やパンタを装備。前面窓はHゴムで固定され、表情も変わりました。

蹴上ではインクラインを見学。そして南禅寺に参詣します。永観堂から哲学の道を歩いて銀閣寺へ…と言えば3年前の高校の修学旅行を思い出しますが、あの時はいつも近くにMさんがいて…などと、帰らぬ人のことは忘れましょう。とはいえ、昨年の梅雨にYMさんにフラれて以来、大学1年の後半は特定の人への想いも無く、ただ「恋に恋して」いた時期だったようです。銀閣寺を見学した後は、「銀閣寺道」電停から2系統の市電に乗りましたが、南方の京都駅前へ行くのに電車は北へ向かっています。この後すぐに交差点を左折して今出川通を西へ進み、「河原町今出川」でまた左折して河原町通を南下することになります。もっとも、自分たちは真っ直ぐ京都駅へは行きませんが。

2系統の市電を「河原町五条」で下りて、五条大橋を渡ります。鴨川と京阪電車が同時に見渡せる好きな光景なので、今回は心おきなく写真を撮ることにしました。七条からやって来た電車は…おや? これは1900系ではありませんか。かつての特急車。自分が京阪のファンになった切掛けでもある、テレビカーも連結した、洗練されたスタイルの車輛でした。それが今や、オレンジと赤の特急色でなくなったばかりか、3扉化されて普通車に格下げされ、悲しく思います。以前、京阪特急を撮った際は1810系からの編入車だったので、新造1900系の特急時代の姿も是非撮りたいと思っていましたが、果たせませんでした。それでも、改造後も優美なスタイルですし、緑の濃淡の塗装も綺麗ですね。

来ました~、京阪特急♪ 前回格下げ後の姿を見た1900系の後を継いで、昭和46年以降の看板列車となった3000系です。伝統のテレビカーも、カラーテレビに格上げされました。また、一斉自動転換クロスシートは世界初だそうです。この日、大阪の淀屋橋駅で、折返す際のシート転換の様子を実際に見て感動しました。そして乗込んだテレビカー。平日の午前中ということで、放送されていたのは幼児番組でしたが、それでも喜んで視聴しながら、先頭車の最前列の座席で前方の展望も楽しみつつ、終点の京都三条まで乗り通しました。もっとも、テレビを見上げるには少々首が痛くなる席でしたが…。それにしても、当時は電車内でテレビを見るなど、普通には考えられないことでした。

五条通から南を見た場面。このアングルでは、いかにも京阪電車が川の中の堤防上を走っているように見えますが、線路の右が鴨川で、左は琵琶湖疎水の一部区間(鴨川運河)です。現在は疎水が暗渠化されて道路になっていますから、比べようとしても場所は少し異なり、やや西へ寄った五条大橋の上からになりますが、似たような雰囲気は出ているように思えます。右端に京都タワーが見えることにも変わりはありませんね。3000系の特急車は、スタイルも色も惚れ惚れするような素敵な電車で、後には富山地方鉄道や大井川鉄道にも譲渡されて活躍します。京阪に最後まで残った1編成は、中間にダブルデッカー(2階建)に改造した特別車輛を挟んで走りました。

五条通を東山方向へ少し行った所から京阪の線路を振り返ります。当時は歩道橋があったのですね。横切る5000系のサイドビュー。本邦初の5扉車ですが、3年前の修学旅行の際に初めて見た時は夜で、きちんと撮れませんでした。この写真も側面だけですが、日中には座席が下りて締切となる各車輛2箇所のドアがステンレスの地肌を見せていることは、カラーなので良く分かりますね。踏切の手前は鴨川運河ですが、後に南北の道路に変わって、ここは交差点になりました。さて、この後はS君と清水寺界隈を歩き、市電で京都駅へ出て、新幹線で先に帰る彼を見送りました。自分はまた和歌山の姉の家へ戻り、翌日からは自由気ままに、一人で動き回ることになります。

この日は和歌山線に乗って吉野口で乗換え、一日たっぷり飛鳥を歩きました。翌3月6日は紀伊風土記の丘を一人で歩いていると、幼稚園の先生という年上女性に逆ナンパされて和歌山城などを散歩。たこ焼きをご馳走されて、その先も誘われたものの少し怖くなり、別れて帰ってから後悔した純情青年さっしいでした。7日は野上電鉄に乗ったのに写真を撮らなかったという大ボケ。9日には東京へ帰りました。【大学1年編・終】/4月からは大学2年生。相変わらず「ハモソ」漬けの日々ですが、この年の秋には、自分の人生の中でもかなり重要な恋をします。鉄道写真が無いので詳しく書く機会がありませんが、高崎線の客車列車で桶川へ…など、知る人ぞ知るエピソードも生まれました。

昭和51年も一気に年末まで来てしまいました。中学時代の友人Y君と関東平野を歩く、恒例の「年末小旅行」も、この年で6回目。今回は東武熊谷線で妻沼(めぬま)を訪れましたが、キハ2000形の写真はこの1枚だけ。今から思えば、何とも勿体ない話ですね。鉄道への興味よりも野山歩きが優先し、更には「鉄より柔らかいもの」に惑っていた時代であったことが分かります。この年の夏に音楽サークル「ハモソ」で、2年の僕たちが企画して秩父鉄道沿線へキャンプに行き、その時に急速に親しくなったTさん(国立某女子大学生)と11月3日に初デート。その後は彼女に振り回される日々でした。この2日後の大晦日も二人で明治神宮に「終詣」して、新宿西口で一年最後の夕陽を一緒に眺めます。

東武熊谷線は、熊谷から妻沼まで、ほぼ真北へ向かって走る10.1kmの非電化路線です。開業は意外に新しく、昭和18年。妻沼の先は利根川を越えて群馬県へ渡り、対岸の仙石河岸(せんごくがし)貨物駅に接続して小泉線に繋がる路線の一部になる予定でした。その未成区間は路盤がほぼ完成し、まるで廃線跡を辿るように歩くことができました。途中には小道を跨ぐ立派な橋台もあります。Y君との「年末小旅行」も、初めのうちは上武鉄道や関東鉄道常総線や東武の根小屋貨物線跡など、僕の鉄道趣味に付き合ってもらうような内容でしたが、4回目の館林以降は純粋な関東平野歩きにシフトしています。6回目のこの日も、後半は歴史を辿りながら野山歩きを楽しむ日となりました。

これはまた衝撃的な光景ですね。妻沼から更に北を目指していた東武熊谷線ですが、利根川を渡る鉄橋は着工し、橋脚が立つまでに至っていました。ざっと数えて20本以上はあり、対岸の群馬県側には橋台も見えています。しかし、この時点では既に何年も放置されており、程無く全て撤去されてしまいました。北の仙石河岸貨物駅は、西小泉からの貨物線と共に、この年の10月に既に廃止。南の熊谷線も昭和58年には廃止されてしまいます。仙石河岸駅の跡を訪ねるのは18年も後の平成6年のことで、この日はバスで太田へ。万葉集で新田山(にいたやま)と呼ばれた金山に登り、金山城跡や新田神社を訪れました。そして、Tさんとは不思議な関係のまま、昭和51年は幕を閉じます。

Tさんとの関係もそのままに年を越して、昭和52年を迎えました。松の内に二人で鎌倉へ行き、冬の日差しが明るい砂浜でじゃれ合ったり、いろいろありましたが、結局2月19日に破局を迎えます。池袋駅で左手の握手。僕はそのままY君の家を訪ね、西城秀樹の『ラストシーン』をカラオケで歌いました。終わって初めて「恋だった」と気付いた日です。翌日は、急遽Y君との「関東小旅行」。なぜか筑波山を眺めたかったので、関東鉄道常総線に乗って茨城県の下妻を訪れました。3か月ばかりの恋でしたが、表情には悲しみが溢れています。下妻駅の常総線は、夕暮れのボケ写真。それでもハモソでは幹事学年となり、3月末の合宿で気合を入れて、新年度に向けて出発です。【大学2年編・終】

いきなり真夏になりました。早稲田大学ハーモニカ・ソサエティー夏の演奏旅行。この年は自分たち幹事学年(3年)の企画で「信濃路サマーコンサート」と題するドサ回りをしました。学生の貧乏旅なので、7月25日は新宿発・長野行きの夜行普通列車。眠れぬままに朝を迎えて辰野で飯田線に乗換え、26日は伊那中学校、27日は伊那市民会館で演奏会。28日は長野へ移動しますが、途中の松本では乗換の合間に、大学で一番の親友となったM君と駅蕎麦を。先輩N氏も特別参加です。80系で行く篠ノ井線は、冠着(かむりき)トンネルを抜けた後の車窓風景が素晴らしく、スイッチバックで上りの急行と単線交換をしたここは、今は無き羽尾信号場だと思えるのですが、如何でしょうか?

長野電鉄に乗って須坂へ来ました。夜の演奏会に備えて須坂市民会館でリハーサル。本番では自分がアレンジしたピンク・レディーの曲なども評判が良く、熱気のあるコンサートになりました。ラストは僕のクロモニカ・ソロ演奏による、ビートルズの『The Long And Winding Road』。万雷の拍手に感激です。自分の青春時代の頂点とでも言えそうな日でした。この後も(勉強はせず)ひたすらハモソに打ち込みますが、それとは裏腹に、鉄道趣味までは手が回りません。この年に撮った鉄道写真は、これが最後。なんと1年間で3枚ですから驚きます。余談ながら、これより前の6月には、知る人ぞ知る(知らない人は知らない)「上野駅13番ホーム・夜行急行出羽の別れ」などもありました。